高知の路面電車『とさでん』が
愛される理由とは?歴史は?特徴は?
というわけで今回は、高知の路面電車「とさでん」ってどんな電車?について調べてみました。
はい、全国の地方都市60カ所以上を実際に飛び回って磨いた好奇心アンテナを持つ「ことばと」がお伝えします。最後までよろしくお願いします。
まずは予告編の紹介文です。
ドキュメント72時間 高知 路面電車に揺られながら
高知市を東西南北に貫いて隣の市町まで。開業から121年、地域の人たちの暮らしを支えてきた路面電車に乗り込んだ。通勤、通学、病院に買い物、生活のために必要だから乗るのだけど、聞くといろいろな事情が。本を読むため、昔の仲間と飲むため、くねくねと走る風景をただ眺めるため…ただの移動手段ではない何かがそこにはある。さまざまな人生をのせて走る路面電車でともに揺られながら、乗り合わせた人々と過ごす3日間の旅。
https://www.web.nhk/tv/an/72hours/pl/series-tep-W3W8WRN8M3/ep/MKR5QR95XJ
今週10/3(金)夜10:00#ドキュメント72時間
— ドキュメント72時間 (@nhk_72HR) September 30, 2025
高知🚋路面電車に揺られながら
60年選手のベテラン車両🚃から、ヨーロッパのトラムのような新型車両🚊まで。どれも味わいがあります。担当は柴田D(高知局)。取材・撮影で全路線を何往復もして、だいぶ詳しくなったとか… pic.twitter.com/tDUxLMyd29
【ドキュメント72時間】日本一長い路線網を誇る『とさでん交通』
「とさでん交通」は、高知県中部を走る路面電車・バス事業者です。2014年10月に土佐電気鉄道と高知県交通、土佐電ドリームサービスの3社が経営統合して誕生しました。コーポレートカラーのグリーンとオレンジには、高知の豊かな自然と太陽の明るさが表現されています。
- 会社名: とさでん交通株式会社
- 路線網: 総延長25.3km(日本一長い路面電車路線網!)
- 路線:
- 桟橋線(高知駅前~桟橋通五丁目/3.2km)
- 後免線(後免町~はりまや橋/10.9km)
- 伊野線(はりまや橋~伊野/11.2km)
- 最長区間: 後免町〜伊野間 22.1km(片道約1時間半!)
- 車両数: 14形式63両(国内外のバラエティ豊かな車両)
後免町停留所から伊野停留所までの通し運行。なんと22.1kmを1時間半かけて走る、日本最長の路面電車運行区間なんです。これはもう、路面電車というより小旅行の領域じゃないでしょうか。
高知では、JR四国や土佐くろしお鉄道を「汽車」、とさでん交通を「電車」と呼び分けるそうで、地元の人たちの生活に深く根付いている様子が言葉からも伝わってきますよね。
【ドキュメント72時間】時代を超えて走り続ける高知の路面電車
高知の路面電車の歴史は古く、1904年(明治37年)に土佐電気鉄道として開業しました。実に120年以上の歴史があります。当時は「高知市街軌道」という名称でした。
この長い歴史の中で、高知の路面電車は何度も危機を乗り越えてきました。1980年代には全国的に路面電車の廃止が相次いだ中、高知では市民の足として生き残りました。もちろん経営の荒波にもまれることも。2014年の経営統合は、土佐電気鉄道と高知県交通の両社が累積赤字約90億円という厳しい状況に追い込まれた結果でした。
県と市町村が出資する第三セクター方式で再スタートを切った「とさでん交通」。その名前は公募で決まったもので、1235点の応募の中から選ばれました。「土佐」と「電車」を組み合わせた愛称「とさでん」に「交通」を加えた名前には、地元の人々の熱い思いが込められています。



世界中から集まった電車たち──これぞ「走る博物館」
ノルウェーから来た「金魚電車」
さて、ここからがことばと的に最も興奮するポイントです。とさでん交通には、なんと3カ国から導入された外国電車が走っているんです。もう、これ反則級の面白さじゃないですか?
まずはノルウェーのオスロ市電から来た198形。1939年製の流線型車両で、裾がイルカの口のように見えることから現地では「金魚電車(ゴールドフィッシュ)」の愛称で親しまれていました。1985年まで現役で活躍した後、土佐電気鉄道の開業85周年記念事業として高知へやってきたんです。
デッキ付き、横引きカーテン、1+2列のクロスシート。座り心地は路面電車とは思えないゆったり感。天井にはノルウェーの地図やノルウェー語の詩まで描かれていて、高知にいながらにして北欧旅行気分が味わえるという、なんとも贅沢な電車なんです。
ノルウェー・オスロ市営鉄道198号
— とさでん好き (@tosaden_fan) October 20, 2024
現在では、とさでんの中で最年長の車両です。屋根には綺麗なオーロラがありますよ!#とさでん交通 #路面電車 #外国電車 pic.twitter.com/ptpB34Lcts
オーストリアのグラーツから
深緑色が特徴的な320形は、オーストリアのグラーツ市電出身。1949年製で、50両も製造された人気車両でした。1992年に高知へ導入された際、ロングシート化されましたが、非常に大きな側窓と豪華な横引きカーテンはそのまま。
窓の開閉方法がまた素敵で、ハンドルを回して開閉するんです。まるで「オリエント急行」みたいじゃないですか。天井にはオーストリアの地図も描かれていて、ヨーロッパの香りがぷんぷんします。
やっと晴れの日がきた〜☀️ #とさでん交通
— とさでん好き (@tosaden_fan) August 31, 2024
#グラーツ市電 #路面電車 #外国電車 pic.twitter.com/7vY4ScLleG
ポルトガルのリスボン市電は最高級
そして極めつけが、ポルトガルのリスボン市電から来た910形。1947年イギリス製で、「凸」の見た目が特徴的です。1990年に導入された際、大規模な改造が施されました。
転換式クロスシート、横引きカーテン、デッキ付き、立派な木製の扉。田村里志車両工場長の言葉を借りれば、「全国の数ある現役路面電車の中で、おそらく最も豪華な内装」。これはもう乗るしかないでしょう。
なぜ外国電車を導入したのか
車両工場長の田村氏によれば、導入の理由は明確でした。「モータリゼーションの影響による乗客減少に歯止めを掛けるべく、路面電車先進国であるヨーロッパの電車を高知で走らせたら観光客が増え、増収につながるのではないかと考えた」とのこと。
部品は購入時にある程度確保し、メンテナンスをしながら繰り返し使用。現在は通常営業での運行はしていませんが、毎年5月の「電車の日」イベントで披露され、貸切電車としても全国の鉄道ファンから高い人気を誇っているそうです。
国産電車も新旧バラエティ豊か
外国電車だけではありません。国産電車も実にバラエティ豊かなんです。
1905年製の7形を細部まで再現した「維新号」というイベント用電車もあるんですよ。明治から令和まで、まさに走る日本電車博物館ですよね。
後ろから視線を感じる・・・#とさでん交通 #路面電車 #維新号 #外国電車 pic.twitter.com/zEIpQZa2tZ
— とさでん好き (@tosaden_fan) October 14, 2024
超低床電車も導入されていて、バリアフリー化にも対応。古い車両を大切に使いながら、新しい技術も取り入れていく姿勢が素晴らしいじゃないですか。
とさでんの魅力をまとめて:高知の宝物を再発見
こうして振り返ってみると、とさでん交通の路面電車は、高知の日常を豊かに彩る存在ですよね。最後に、その魅力を3点にまとめておきましょう。
- 日本最長の路線網: 25.3kmをくねくね走る旅は、移動を超えたリラクゼーション。番組のように、風景を眺めるだけで心が癒されます。
- 多様な車両の宝庫: 外国産中古電車が織りなす異国情緒が、観光の目玉。地元民の足としてだけでなく、ファン心をくすぐるんですよね。
- 地域を支える歴史と未来: 121年の歩みと統合のドラマが、公共交通の重要性を教えてくれます。バリアフリー化も進み、これからも頼もしい存在。
今後、ますますの活躍を期待しています。高知を訪れたら、ぜひ乗ってみてくださいませ。
ありがとうございました。
『ドキュメント72時間』の人気記事3連発!見てね〜👇
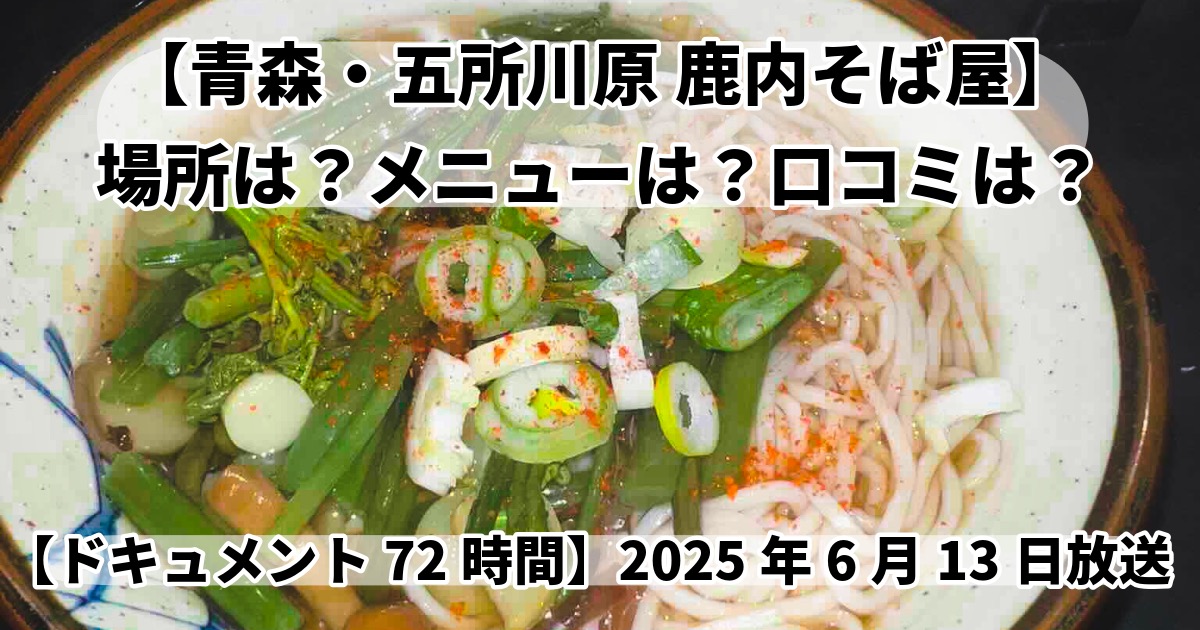
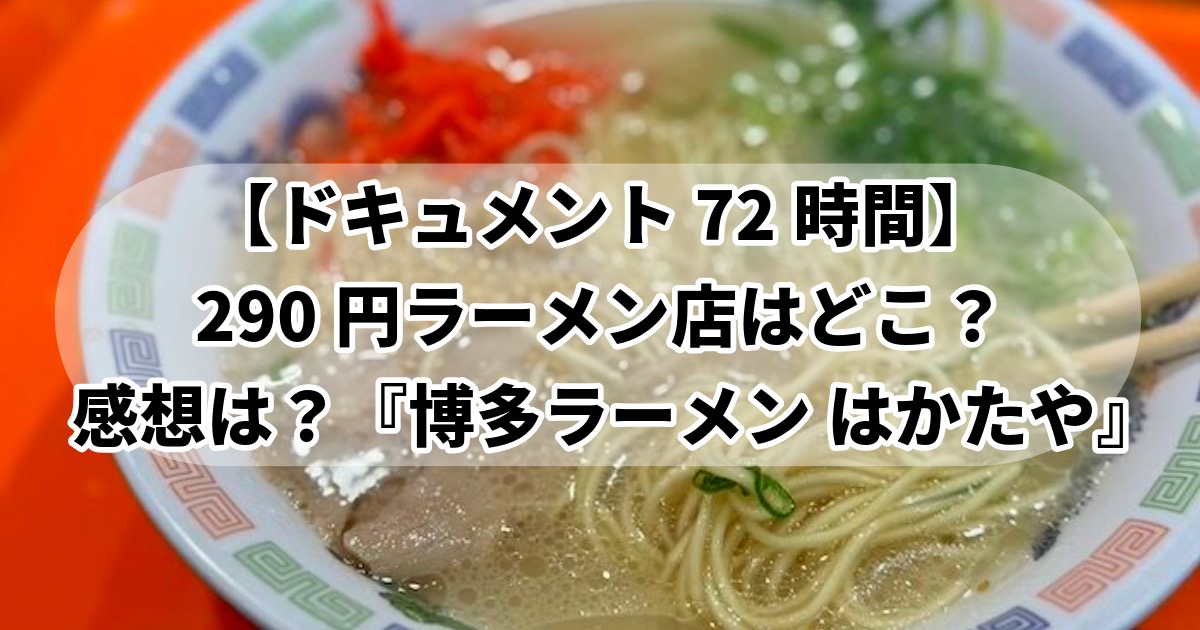
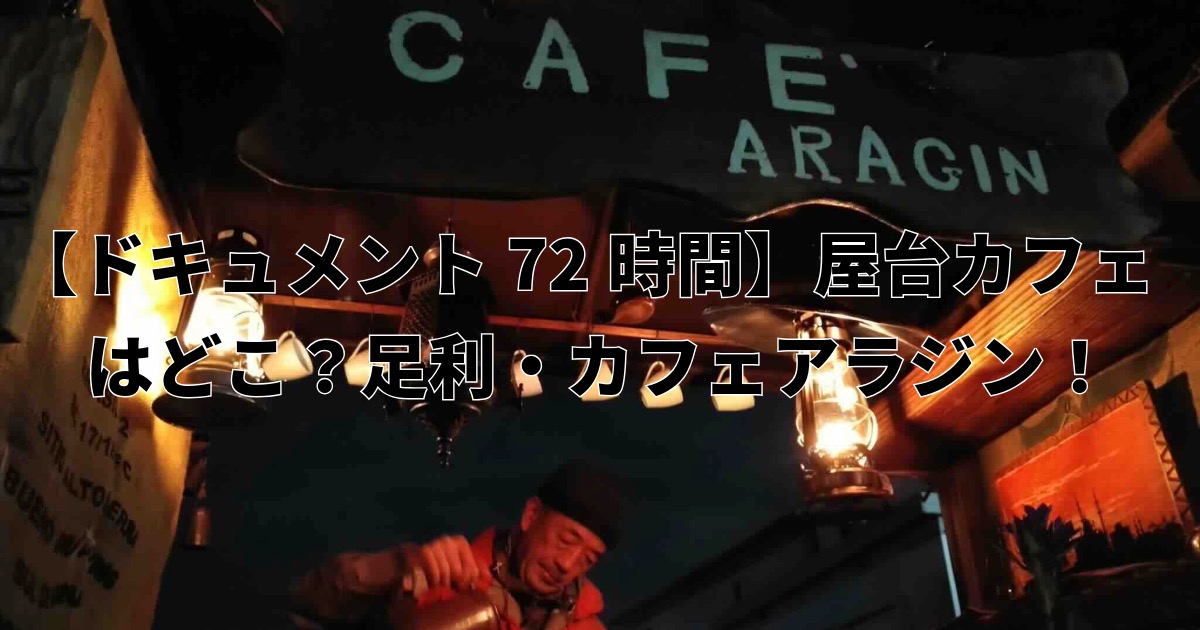

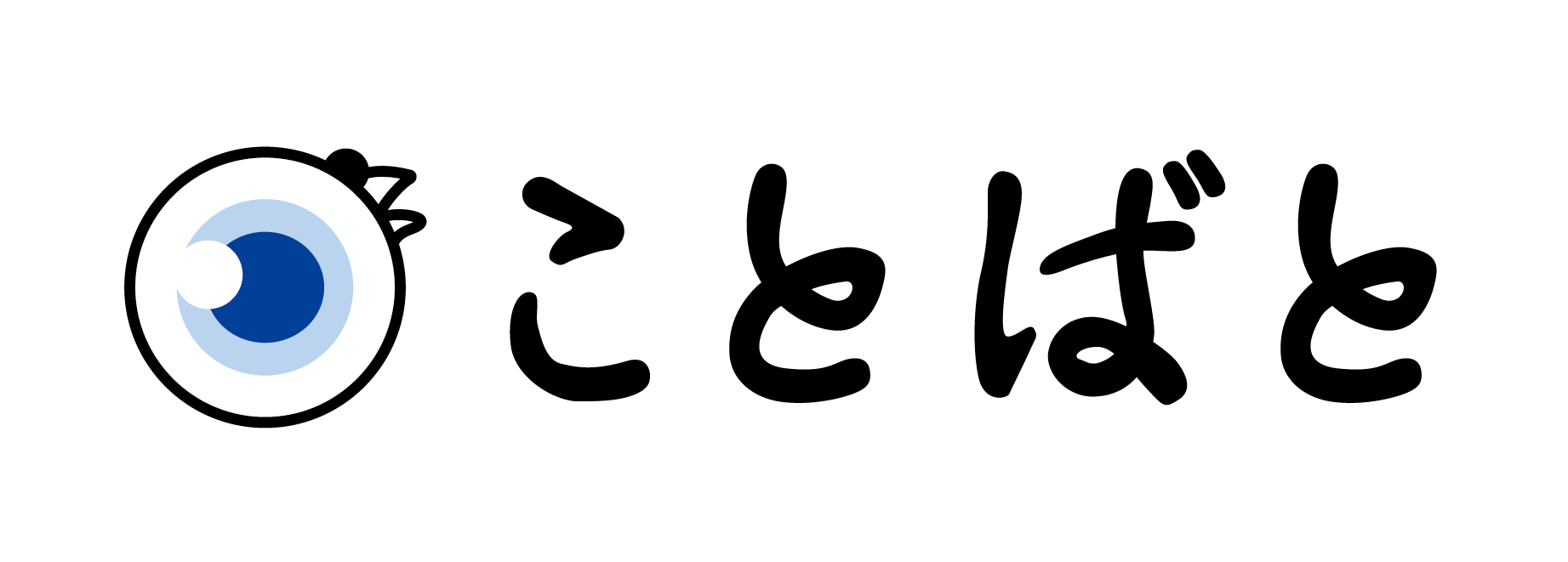



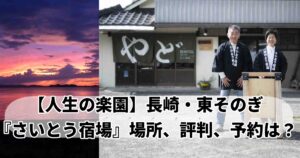
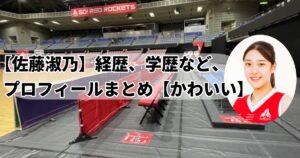


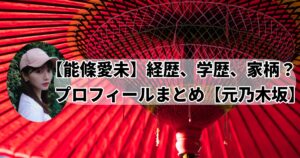
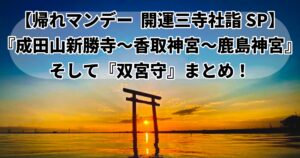
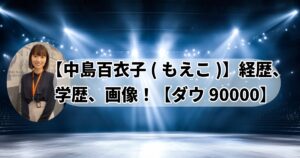
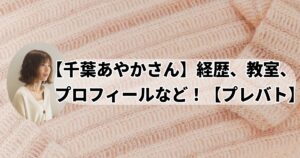
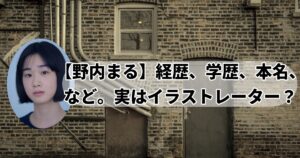
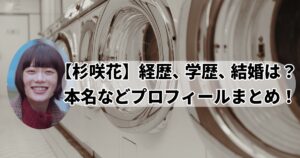
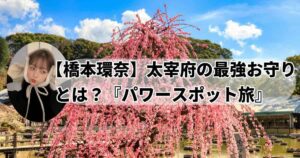


コメント